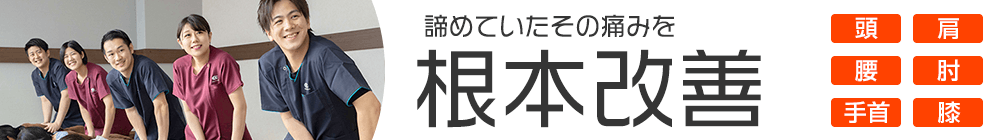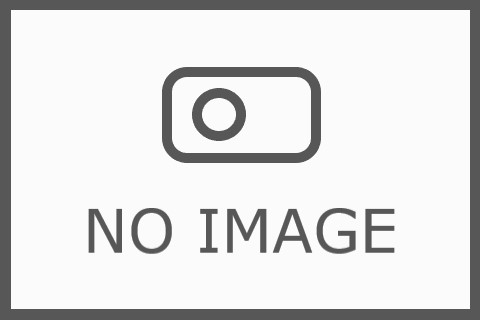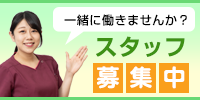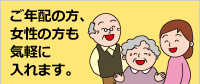巻き肩
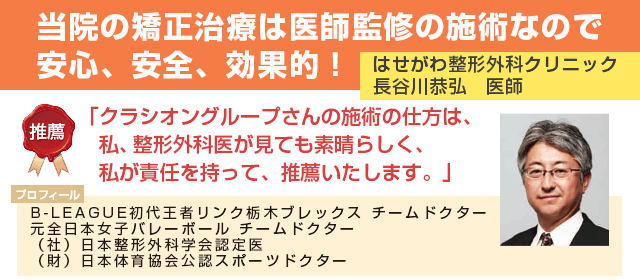

こんなお悩みはありませんか?

肩や首のコリがひどく、慢性的な痛みが続いている
頭痛が頻繁に起こり、仕事や日常生活に支障を感じる
呼吸が浅く、深呼吸がしづらいと感じる
姿勢が悪く、猫背や巻き肩が気になっている
肩を動かしにくく、四十肩や五十肩のような症状がある
腕や手にしびれが出たり、冷えを感じることがある
疲れやすく、集中力が続かないと感じる
巻き肩について知っておくべきこと

【巻き肩の原因】
・長時間のデスクワーク・スマホ使用
前かがみの姿勢が続くと、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が縮まり、肩が前に出やすくなります。
・筋力バランスの崩れ
背中の筋肉(僧帽筋、菱形筋)が弱まり、胸の筋肉が硬くなることで肩が前に出やすくなります。
・姿勢の癖
無意識に肩をすくめる、丸めるクセがあると、巻き肩が固定化されやすいです。
・ストレスや緊張
ストレスが多いと肩がすくみやすくなり、前に巻き込まれる状態が起こりやすくなります。
【巻き肩のセルフチェック方法】
・壁立ちチェック
壁に背をつけて立ち、かかと・お尻・背中をつけます。このとき、肩が壁につかない、または手のひら1枚分以上の隙間がある場合、巻き肩の可能性が高いです。
・腕の位置チェック
力を抜いて自然に立ちます。手の甲が前を向いている場合、巻き肩の可能性があります(正常な場合、親指が前を向きます)。
症状の現れ方は?

【初期症状(違和感・軽いコリ)】
・肩が前に出ている感じがする
・長時間のデスクワーク後に肩や首が張る
・姿勢を正そうとしてもすぐに戻る
この段階では自覚症状が少なく、日常生活に大きな影響はありませんが、放置すると悪化しやすくなります。
【慢性的なコリや痛みの発生】
・肩こり・首こりが慢性化する
・頭痛が増える(特に後頭部やこめかみ周辺)
・背中や肩甲骨あたりが張って痛む
・疲れやすい
この頃になると、筋肉が硬くなり、ストレッチやマッサージをしてもすぐにコリが戻ることが多いです。
【姿勢の悪化、動かしにくさ】
・猫背が定着し、見た目が悪くなる
・肩の可動域が狭くなり、腕を上げにくくなる
・呼吸が浅く、息苦しさを感じる
・この段階では肩関節の可動域が狭まり、巻き肩が固まることが多いです。
【重度の症状(神経症状・機能障害)】
・肩や腕にしびれやピリピリした痛みが出る(胸郭出口症候群の可能性)
その他の原因は?

【運動不足や不適切なトレーニング】
背中や肩回りの筋肉が十分に鍛えられていない場合、前傾姿勢になりやすく、巻き肩が固定化しやすくなります。また、運動時にフォームが崩れると筋力バランスが乱れる原因にもなります。
【左右非対称の負荷】
片側だけで荷物を持つ、または片側ばかりを使う動作が多いと、左右の筋肉バランスが崩れて巻き肩が生じることがあります。
【姿勢のクセの形成】
長期間にわたり無意識のうちに肩をすくめたり、腕を前に出す癖がついていると、その癖が固定化して巻き肩の原因となることがあります。
巻き肩を放置するとどうなる?

1、姿勢の悪化
肩が前に向いた状態が習慣化し、猫背が進行することで全体的な姿勢が悪くなり、見た目にも影響が出ます。
2、慢性的な肩こり、首こり、背中の痛み
筋肉が常に緊張した状態になり、慢性的なコリや痛みが生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。
3、可動域の制限
肩関節や背中の筋肉が固まることで、腕を上げたり回したりする動作が制限され、運動機能が低下します。
4、神経や血管の圧迫
肩周辺の筋肉や組織が緊張することで、神経や血管が圧迫され、腕や手にしびれ、冷え、痛みなどの症状が現れる可能性があります。
当院の施術方法について

【温熱療法や電気刺激療法】
温熱パックやホットパックを用いて血流の流れを良くし、筋肉の緊張を和らげる方法です。
【肩甲骨はがし】
当院では、肩甲骨はがしの施術があります。巻き肩の原因となる大胸筋や肩甲骨を支えるローテーターカフという筋肉をほぐし、胸郭を広げることが期待できます。
【姿勢矯正】
肩甲骨はがしが筋肉にアプローチするのに対し、姿勢矯正は骨格にアプローチする施術です。肩甲骨はがしと併用することで、さらに効果が期待できます。
【猫背矯正】
巻き肩の原因として姿勢の崩れ、つまり猫背姿勢も大きく関与しています。猫背の矯正によって肩関節を正しい位置に戻すことを目指します。
軽減していく上でのポイント

1、正しい姿勢の意識と習慣化
日常生活で自分の姿勢を意識し、肩を後ろに引く感覚を持つことが重要です。
2、定期的なストレッチ
大胸筋や肩前部の筋肉を重点的に伸ばすストレッチを取り入れることが有効です。
3、筋力トレーニングの実施
背中や肩甲骨周りの筋肉を強化するエクササイズを行い、筋力バランスを整えることで、肩の正しい位置をサポートします。
4、無理なく徐々に軽減を目指す
急激な変化を求めず、日々の生活の中で少しずつ軽減を実感することが大切です。
監修

さわやか接骨院 石田院 院長
出身地:静岡県藤枝市
趣味・特技:クラシック音楽鑑賞、温泉、サウナ